三角波と消臭剤を持ち歩く 岩根彰子

足利義昭肖像画
「秀吉は日吉丸が嫌い」
秀吉が「関白」となって施工したものに、
「太閤検地」と「身分固定化」というものがある。
太閤検地は、ただ土地の面積と収穫量を調査しただけでなく、
検地帳に登録された耕作者を「百姓」とし、
それを、年貢負担者と定めた。
それまで、実際には耕作していながら「作合(つくりあい)」という形で、
有力農民に中間搾取されていた農民が、
この検地によって、自立したことの意味は大きい。
(百姓出身の秀吉らしい思慮である)
指揮棒が降らせるひらひらの雪 泉水冴子
しかし、農民たちは、それを手ばなしで喜んでいるわけにはいかなかった。
”太閤検地”から矢継ぎ早に、秀吉は”身分統制令”をだす。
これは、侍、中間、小者などが新たに農民や町人になること、
逆に農民が施策耕作を放棄して、
商人になることなどを、禁止したのである。
農民は農民、武士は武士、商人は商人というように、
身分を固定し、それを移動してはならないことを規定した。
次ページのタクトに揺れている呼吸 桂 昌月
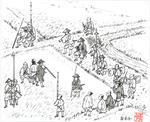
太閤検地
この身分統制より3年早い、天正16年秀吉は、「刀狩り」の令を出している。
これも半農半士的身分を否定したものである。
それまでの農民の場合、
傭兵という出稼ぎもあり、刀や槍の一本や二本は持っていた。
それは便利でもあり、支配権力にとっては、脅威でもあった。
いわゆる、「いつまた下克上の嵐が吹荒れるかもしれない」
という不安があった。
地平線の向うに折れたボクの影 笠原道子
秀吉は、秀吉自身が貧しい農民の出身でありながら、
関白まで上り詰め、自らが天下統一を成し遂げると、
再び自分と同じ人間が、生まれる可能性をなくしたのである。
(本人が下克上でのし上がりながら、下克上の社会を否定したのである)
幾重にも自分にかける包装紙 久恒邦子

秀吉の母・なか(大政所)
「秀吉最初の下克上ーエピソード」
秀吉の母・なかは、夫(秀吉の生父)が死ぬと、まもなく再婚する。
秀吉は新しい継父を嫌い、家を出る。
そして、当時の有力武将、今川義元の駿河をめざした。
浜松まで来て、今川の家来で浜松の出城城主・松下嘉兵衛に出会い、
そこで松下の家来になる。
そして、またたくまに財政担当まで出世した。
曲者は柔和な顔を持っている 内藤光枝
すると先輩たちは、その嫉妬を抱き、
「秀吉は公金を横領している」
と、中傷をしはじめたのである。
嘉兵衛は、秀吉と古い家来の関係が、うまくいかないのを悩み。
そして秀吉を呼び、
「おまえが悪いことをするとは思わない。
しかしおまえがいると、松下家の内部が乱れる。
退職金をはずむから退職してくれ」
と頼んだ。
ケータイが鳴ってる麺もふきこぼれ 山本昌乃
それに対して、日吉丸は、
「部下の潔白を知りながら、古い家来の圧力に負けて、
わたしを首にするあなたには、リーダーの資格はない。
そんなあなたに出城をまかせる今川様も、大した人物ではない。
わたしから松下家を辞めます。
退職金はいりません。
なぜなら、主人のあなたが私を首にするのではなく、
部下の私が、あなたを首にするのです」
と応えた。
まさに、秀吉は、ここで一番最初の下克上を実践したのである。
傷口を洗いリセットキーを押す 谷垣郁郎

大河ドラマ・第16回・「お江ー関白秀吉」 みどころ』
秀吉(岸谷吾朗)は、家族を大坂城に呼び寄せ、三姉妹と合わせ、
広間で今後の決意を表明する。
秀吉 「わしも、これだけの城を持てる身分となった。
朝廷より、内大臣に任ぜられてもおる。
こうなったからには、わしは、わしは、将軍になろうと思う!」
それには、さすがの家族も、妹の旭(広岡由里子)を除いて、信じるものはいなかった。
勿論、三姉妹も同じだったが、
なぜ突然そんなことを言い出したのか?
綿密に描く摩周湖の展開図 井上一筒

秀吉は、備後の義昭(和泉元彌)の宿所に秀長を遣いに出す。
義昭 「な、なんたることか。今まで長う生きて参ったが、このように情けなきこと、
かくも大きな屈辱は初めてじゃ・・・。
百姓の分際で、源氏を名乗れる道理があるまいが!
ぬしの如き者、声をかけられるのも不愉快じゃ!」
秀吉にとっては最大の屈辱だった。
「なんとしても、義昭に目に物を見せたい!ひと泡吹かせたい!」
じりじりと間合いを詰めて来る火種 上嶋幸雀
秀吉は、自室に江(上野樹里)と宗易(石坂浩二)を呼び、
「義昭に泡をふかせるいい方法はないか」と聞く。
なかなか妙案は浮かばないとこへ、江がポロッと、
「将軍より偉くなればいいのではないか?」 と言う。
日の本でいちばん偉いのは帝だが、それだけは絶対に無理だ。
では、その次に偉いのは・・・?
「関白」であった。
おーい夕日これからどこの朝日だい 有田一央

関白は、公家の五摂家から選ばれるので、武家からは出たことがない。
そこで、秀吉は五摂家の筆頭・近衛家に目をつけた。
近衛龍山(江良潤)に会うと、莫大な財力にものをいわせ、猶子となる。
次は、関白になる番だ。
そんなとき、大坂城に来た細川忠興(内倉憲二)から、
いい情報が届く。
さあ春だコーヒーカップ回り出す 太田扶美代
現在の関白である二条昭実に対して、
近衛信尹(のぶただ)が、退位を迫っているというのだ。
信尹は、秀吉が猶子となった龍山の嫡男、
つまり、秀吉と信尹は兄弟ということになる。
さっそく信尹に行くと、やはり莫大な金銀財宝を与えた。
三成 「近衛様と二条様どちらが関白の座を得られましょうと、
あとには必ずや禍根が残るはず。
しかしながら、前例なき武家関白であれば、恨みつらみは出ませぬ」
理由はどうであれ、大量の財宝を見せられたら、信尹も断るわけにはいかなかった。
とうとう秀吉は関白になった。
ギャグひとつ許せない日と許せる日 片岡加代
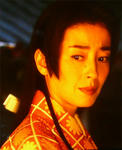
そのことを聞いて驚いたのが義昭だった。
義昭 「・・・ひひ、秀吉が関白じゃと・・・? 猿が関白? 百姓が・・・。
そのようなこと、この世にあってなるものか! さ、猿が関白・・・」
京の妙顕寺城で、御所の使者を迎えた秀吉は、
束帯を着けたまま、大坂城の茶々(宮沢りえ)のところに駆けつけた。
さわやかな音符に乗って来た言葉 奥山晴生

秀吉は、誰よりも先に茶々に見せたかった。
秀吉 「拙者、こたび、関白に任じられることになりましてござりまする」
茶々 「聞き及んでおりまする。・・・おめでとう存じまする・・・」
そんな秀吉を見て茶々は呆れていたが、
その目は明らかに、これまでの秀吉を見る目とは違ってた。
江は、茶々の心変わりを感じ取っていた。
目が合ってしまった 愛してしまった 前中知栄
 [5回]
[5回]
