骨肉の盥はまいにちがドラマ たむらあきこ

お福(春日局)
「将軍の乳母・お福」
秀忠が伏見城に朝廷からの使者を迎え、
将軍に任命されたのは、
慶長10年(1605)4月16日のことである。
御台所・お江が、誕生した年でもあった。
その前年にお江は、
秀忠の世継ぎとなるべき男児を産んでいた。
竹千代の名前が与えられた、後の3代将軍・家光だ。
お江にとっては、初めての男の子である。
雲ちぎって獏一頭編みあげる 岩田多佳子
この時代、上級の武士は子供が生まれると、
「生母に授乳させるのではなく、乳母を付けるのが普通だった」
当時は、授乳次第で、
子供の成長が大きく左右される、
医学水準だったことに加え、子育ては、
「妻が家において何より優先すべき役割」 とは、
必ずしも考えられていなかった、社会風潮が背景にあった。
山道の梔子沈黙を零す 岩根彰子
竹千代を産んだ江は、その乳母の選定について、
「東国の女性は気性が荒い、京都近辺の女性がいい」
と指示を出した。
そこで京都所司代の板倉勝重が、人選に当たることとなり、
「公募」の立て札を諸所に立てた。
応募してきた中に、福もいた。
結果がどうなろうと、誰が選ばれようと、
勝重にまかせたことだから、江は、受け入れざるを得ない。
愚かさの中になんじゃもんじゃの種 前中知栄

春日局
≪文京区礫川公園に”誰にも負けないぞ”という表情をみせている≫
結果、竹千代には、
稲葉正成という武将の妻・お福という女性が、
乳母につけられた。
後の、春日局である。
お福の夫・正成は、関が原の戦いで、
家康の勝利に、おおきく貢献した小早川秀秋の重臣だったが、
お福が乳母になった頃は、
小早川家を去り、浪人の身だった。
その時すでにお福は、正成との間に3人の子供を儲けていた。
ちょうど、三男の正利が生まれた頃、
乳母に指名された格好である。
帯の芯女ひとりの火山帯 板野美子
そのお福が、なぜ、その任に就くことができたのか、
はっきりしたことは分からない。
「家康の愛妾だった」 という説もあるが、
ただ、乳母になるに当たっては、
夫・正成とは離縁する形をとっている。
この離縁についても、
夫が浮気したので怒った福が、刺し殺したとか、
諸説あるが、ほとんどが江戸時代の創作であり、
確かなことは、分かっていない。
生涯のいま午後何時鰯雲 大西泰世
いずれにせよ当時の乳母の地位は、決して軽いものではなく、
実母より強い絆で、結ばれているケースもあった。
家光と春日局も、そのような関係にあり、
家光は、実母の江よりもお福を慕い、
強く信頼していたという。
≪「春日局」の称号は、寛永6年(1629年)10月10日に、
さまざまな画策の経路を経て、朝廷から賜ったものである≫
慕われているしあわせの髪を梳き 時実新子
御台所である江と、
家光の養育をめぐって、対立したとも言われているが、
これにはお福の出自が、関係しているのかもしれない。
お福の父は、斎藤利三という明智光秀の家来だったが、
”本能寺の変” 後の ”山崎の戦い”で秀吉に敗れ、
光秀とともに、六条河原で処刑され、首を晒された。
その首を涙をいっぱいためて、見上げていたのが、
まだ幼かった福である。
その秀吉の養女でもあった江に、
恨みを抱いていたとしても、不思議ではない。
A型の鬼としばらくおつきあい 森中惠美子
だが、お江もまた、父・浅井長政が同じように、
罪人としてその首級を晒され、
お福と同じような境遇にいるのだ。
一方的な思い込みで、対立軸を太くするお福は、
かなり、「直線的で、負けん気の強い性格」
の女性であったものと推測できる。
それは、将軍の権威を背景に、
老中をも上回る、実質的な権力を握り、
権謀術数が渦巻く「大奥」という世界で、
隠然たる権力をふるっていく姿にも、
顕著にあらわれている。
ぺちゃんこのところに触れてゆく鳥語 ひとり静

歌舞伎「吹上御庭花見の場」錦絵
慶長11年9月、新築・江戸城・本丸御殿で
秀忠とお江の新しい生活が、始まると同時に、
お江が取り仕切る「大奥の歴史」もここに始まった。
大奥というと、
とりわけ男性の出入りが、制限されると言われるが、
この頃は、男性の出入りも結構みられたようだが・・・。
大奥を、江の手から、春日局が取り仕切るようになり、
出入りが極度に厳しい空間に変貌する。
責任の範囲で白粉をはたく 山本早苗


大河ドラマ・「お江」-第38回-「最強の乳母」 あらすじ
慶長9(1604)年7月、
江(上野樹里)は待望の男子を産んだ。
徳川の世継ぎの幼名・
「竹千代」と名付けられたその子を囲み、
秀忠(向井理)もヨシ(宮地雅子)も大姥局(加賀まりこ)も、
満面の笑みを浮かべる。
それを見た江は、
やっと肩の荷が下りた思いで、心から安堵した。
無花果の花ひらり人間になった 河村啓子
だが、和やかな時間は長く続かない。
竹千代の乳母として、
家康(北大路欣也)が送り込んできた福(富田靖子)が現れ、
挨拶もそこそこに、竹千代を連れ去ってしまったのだ。
まだ床に伏せっていた江は、
福に抱かれた息子が去るのを、
ただ見送るしかなかった。
伏線に動かぬものを潜ませる 内藤光枝

やがて、江が床上げしても、
福は何かと理由をつけて、彼女を竹千代に近づかせない。
江は、そんな福の態度に少し異常なものを感じ、
不安を覚えた。
はたして福は、乳母としてふさわしい人物なのか・・・。
字余りのようなだるさに落ち着かず 新川弘子
そこで江は、感じている不安と、
思うように竹千代を抱けない不満を、秀忠に打ち明ける。
しかし彼は、
「やきもちだな」
と言って取り合わない。
風になったか雲になったか あなた 森田律子
ならばと、江は、家康に宛てて文を書くことにする。
「竹千代の乳母を替えてくれるよう」
頼むために。
それからしばらくして、
家康が京・伏見城から江戸へ戻ってきた。
江は早速、家康に、「乳母を替えることができるか」
確かめるが、家康の判断は、
「福をそのままでおく」 というものだった。
落花生ポリポリ会いたい人が遠ざかる 合田瑠美子
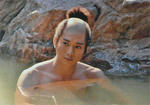
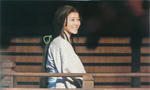
がっかりした江。
そんな彼女に、追い打ちをかけるかのように、
家康が衝撃的な話を切り出す。
なんと秀忠に、「将軍職を継げ」というのだ。
将軍職を継ぐよう言われた秀忠は、
自分の考えを整理する時間が、欲しかった。
そこで江とともに熱海へ向かう。
熱海といえば温泉。
ゆっくり湯につかれば、頭もほぐれると思ったのだ。
首置き忘れましたか秘湯の足湯 山口ろっぱ
『余談』
実は、熱海温泉は、家康ゆかりの温泉である。
家康自身が逗留した記録が、残っているほか、
病気療養中の大名に、
熱海の ”湯” を送ってもいる。
≪また秀忠についても、家康の影響からか、
たびたび湯治に行っていたとか、温泉好きだったという、説もある≫
朝食に琵琶湖 夕食に比叡山 清水すみれ


豊臣の紋 徳川の紋
一方、淀は、甥である竹千代の誕生を知って不安になる。
後継者に世継ぎができたことで、
秀頼(武田勝斗)に、「政権を返す」 と言った家康の、
気が変わるかもしれないからだ。
だが、秀吉の七回忌に京で行われた祭りの様子を聞き、
不安は解消される。
パニックのところどころに酔芙蓉 赤松ますみ

祭りは大盛況で、人々は
今も秀吉を慕い、懐かしんでいるとか。
豊臣家の威光は衰えておらず、
家康はいずれ、政権を返上せざるえないだろう。
淀はそう思ったのだ。
同じ頃、家康にも祭りの様子が伝わる。
そして彼も、改めて豊臣家の存在の大きさを感じていた。
「徳川の世になった」 と天下に示さなければならない。
そう考えた家康は、
秀忠に将軍職を譲ることを思いついたのだ。
野仏が見ている雲は流れてる 和田洋子
 [9回]
[9回]
