てのひらで地球を思いきり絞る 森中惠美子

薩長同盟の調印式の場
幕末当時の”薩長の敵対意識”は、
現代のわれわれの想像を、はるかに超越するほど、
凄まじいものだったと思われる。
敵対とはいえば、即座に頭に浮かぶのが、米ソの冷戦。
しかし、米・ソの場合は、あくまでも冷戦。
ところが、薩長の場合は、
実際に戦場でガチンコ勝負しているのだ。
特に、長州の”反薩摩感情”は、相当なものだったはず。
十二指腸にカギ裂きができるまで 井上一筒

禁門の変
幕末の政争で、ことごとく前に立ちはだかり、
藩をこなごなにする直前まで、
長州を窮地に追いやった張本人が、薩摩でしたから・・・。
文久政変、「禁門の変」によって、
長州なりの正義とプライドは完全に打ち砕かれ、多くの人材も失った。
”犬猿の仲” などという代名詞だけでは、言いあらわし難い。
頂点の薩摩に、どん底の長州。
どう贔屓目に見ても、両藩が結びつく要素はなかった。
簡単に結びつくことを許さない、”感情の決裂”があったのは、
歴然としている。
昨日今日生まれたわけでない殺意 片岡加代

高杉晋作と龍馬(同盟へ一歩前進)
慶応期の、両藩の圧倒的な政治的地位の格差などを、考慮すれば、
薩摩の援助なければ、
長州は何時つぶれても、おかしくはなかった。
その両者が、結びつくことは、まさに予想外のことだった。
目の前のビルは随分遠かった 井丸昌紀
もちろん、”犬猿の仲”の薩摩と長州の仲をとりもつのは、
並大抵のことではなかった。
龍馬も最初は、失敗している。
中岡慎太郎と連携し、龍馬は下関へ向かって、
長州の桂小五郎に薩長同盟の、構想と必要性を力説する。
慎太郎は、西郷隆盛に長州との会見の必要性を説き、
下関に向かわせた。
それがうまくいけば、
慶応元年(1865)5月21日に下関で薩長同盟は、結ばれるはずだったが・・・、
流産となる。
討幕にむけ、いずれ薩長は、結束する宿命にあったとは、思うものの、
下関へ向かうはずの西郷が、
政局の急変を理由に、京都へ向かってしまったのだ。
これで桂小五郎は、薩摩と西郷にたいし、さらに不信を抱くようになる。
不発弾ひとつかかえて旅に出る 早泉早人

ここから、龍馬は発想を転換させる。
まずは、両者の経済提携からはじめようと考えたのだ。
この経済提携によって、長州が薩摩に対する態度を軟化させると、
龍馬は、政治交渉を斡旋しはじめる。
当初は、かたくなな態度だった長州だが、
しだいに、
「薩摩との交渉に応じてもいい」という姿勢になってくる。
経済提携が効いたのと、
長州をめぐる軍事事情が、一段と切迫してきたからだ。
峰打ちにしよう重荷を真っ二つに 宇治田志津子

桂小五郎は京都に出向き、「薩摩屋敷」で西郷と交渉に入る。
そこまでお膳立てしたのだから、
龍馬は交渉成立と踏み、遅れて入京したところ、
「依然、交渉に入っていない」 という現実を知る。
薩摩側は、桂を饗応するばかりで、交渉を始めようとしていなかった。
長州に頭を下げてまで、同盟を組みたくはなかったのだ。
この薩摩の態度に桂は憤激し、交渉はふたたび、
決裂寸前となった。
揺れている人のあたりが生臭い 籠島恵子
決裂の危機にあって、龍馬は、西郷を強烈に説得する。
「桂をはじめ長州が、いかに薩摩にたいして感情的になっているか、
ここは薩摩側から、譲歩する必要がある」
と、説くと、西郷も納得。
慶応2年(1866)1月、ついに薩摩と長州は薩長同盟を締結。
まさに、”奇蹟的大回天”を果たしたのである。
プライドを捨てぴったりの面の位置 山本芳男

ユニオン号(イメージ)
そして同年6月、”第二次長幕戦争”がはじまる。
関門海峡での攻防は、
長州にとって、重要な鍵をにぎる戦いであった。
対外的な窓口である下関を、幕府に押さえられてしまったら、
おそらく長州は、壊滅的な状況になってしまう。
この接戦の海の戦いに、
商社でもあり、独立海軍でもある、亀山社中がユニオン号(桜島丸)で、
長州を助けるべく参戦し、
長州を勝利に導く一役を買った。
まさに”龍馬の海軍”が、歴史を動かした瞬間だった。
鉛筆はあしたを待っていられない 大倉久子


長次郎の遺書と写真
『龍馬伝』・第35回ー「薩長同盟ぜよ」 あらすじ
龍馬(福山雅治)は、桂小五郎改め木戸貫治(谷原章介)が、
護衛にとつけた槍の達人・三吉慎蔵(筧利夫)とともに、京に向かう
その途中、大和屋へ寄った龍馬は、
お徳(酒井若菜)に長次郎(大泉洋)を死なせてしまったことを詫び、
写真と遺書を渡す。
信用をされているから胃が痛む 森口美羽

京に着いた龍馬たちだったが、
薩摩藩邸の周りに幕府方の隠密がいて、なかなか近付けない。
一橋慶喜(田中哲司)が、出兵しない薩摩に疑念を抱き、
不穏な動きはないか、探っていたのだ。
しかたなく、寺田屋を訪れた龍馬は、
お登勢(草刈民代)からお龍(真木よう子)が、
「自分に思いを寄せている」 と聞かされる。
お龍の想いを知った龍馬は、
「命の危険を冒して、日本を変える仕事に取り組んでいるから、もう会うことはない」
と告げる。
しぶしぶと 女は横糸をほどく たむらあきこ

8月18日の政変以来、
反目しあっていた薩摩と長州の間に、
一筋のつながりが生まれた。
西郷(高橋克実)から手紙をもらった木戸(桂小五郎)は、
二藩の盟約交渉のため、京の薩摩藩邸を訪れる。
ついに、両藩のリーダーが、初めて顔を合わせることになったのだ。
薩摩と長州が手を結ぶということ。
それは、260年間続いてきた徳川の世に、反旗を翻そうという、
途方もない計画の第一歩だ。
あしたを引っぱる日付変更線 木村禮子

彼らの交渉は、幕府には決して知られぬよう、
しかも迅速にすすめねばならない。
そこで木戸は、
「龍馬が来るまで話し合いを始めない」
と言い出す。
西郷は、問う。
「なぜ龍馬なのか」
ついこの間まで、敵対していた薩摩をおいそれと、信用することはできない。
「この話の立会人ちゅうのは、立場云々ではのう、
何よりも信用できる人間でなくちゃなりません」
木戸の言葉に、西郷も納得する。
構想を練る真夜中の古時計 大倉久子
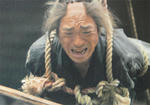
同じ頃、藩の命令で薩摩の動きを探ろうと、
京に来ていた弥太郎(香川照之)は、龍馬と間違えられて、
新選組に捕えられ拷問を受けていた。
お龍の働きで、小松帯刀(滝藤賢一)邸に、西郷と木戸が移ったことを知り、
急ぎ向かう龍馬は、
途中、新選組から放り出された弥太郎を救う。
薩長を結びつける男として、
新選組や伏見奉行に追われ始めた龍馬だったが、
ついに「薩長の盟約」を結ぶことに成功する。
出来そうもないモットーが奇跡呼ぶ 坂下五男
 [9回]
[9回]
