賭けにゆく車窓にガスタンクが見える 森中惠美子

”大政奉還”は慶喜の「高度な政治判断」であったが、その目論見は外れた。
「大政奉還への道」
大政奉還は、徳川慶喜が放った「起死回生の奇策」というイメージで語られてきた。
政権を返上してしまえば、
薩長らの掲げる「倒幕」は、意味をなさなくなるという論である。
たしかに朝廷は、日本全土を統治する能力はない。
外国から一人前の政権として、認められるだけの外交実績もない。
≪まるで現在の民主党(菅政権)の事を言っているようである≫
「薩摩や長州は、しょせんは寄せ集めだから、やがて進退窮まって、
徳川家を盟主とする政権を、作らざるを得なくなるだろう」
そのような「高度な政治判断」で考えた、慶喜の”大政奉還”であった。
橋上にうかつに耳を置いてくる たむらあきこ
「一方、薩土盟約を実現した龍馬らの構想は・・・?」
大政奉還と武力倒幕は、一般的には、対立する概念と思われているが、
そうではない、いきなり幕府を軍事力で倒すとなると、
土佐藩のような親幕府的な心情を抱いている藩は、なかなか踏み切れない。
大政奉還を経ての、新政権構想を掲げることで、
「土佐藩のみならず各藩を次々と巻き込み、事実上、幕府を無きものとしてしまう・・・」
のが龍馬の考え方である。

≪「薩土盟約は、あきらかに幕府を否定している」
「王政復古は論なし」
「国に、二帝なく、家に二主なし、政刑唯一君に記すべし」
「将職に居て政柄を執る、是天地間有るべからざるの理也」≫とある。
太陽に豆板醤をまぜた 石田柊馬
当時、全国のほとんどの藩において、藩内世論が分裂状況にあった。
「揺れ動く」諸藩を、可能なかぎり、
「倒幕」という、ゴールにつながる道筋に引き入れるため、
まずは、幕府に「大政奉還」をさせる。
最後は、徳川権力の廃絶につながっている「渡り廊下」としての、
大政奉還という考え方であった。
渡り廊下に入ってしまえば、
「徳川権力の剥奪」という建物に向かうしか道はないから、
結局は武力倒幕が実現する。
≪”大政奉還しない幕府を倒すこと” と、
”大政奉還して、弱体化した幕府を倒すこと”
を較べれば、明らかに後者のほうがハードルは低いのだ≫
渡らせて淵となりゆく桂川 杉浦多津子

後藤象二郎は大政奉還・「建白書」を幕府に提出する。
慶応3年(1867)10月3日のことである。
後藤は、当時、徳川慶喜は二条城に滞在していたので、
13日には、二条城におもむき、
慶喜の決断を仰ぐために会見におよぶ。
その会見の直前、後藤は龍馬から激励の手紙を受け取っている。
「もし後藤が戻らなければ・・・海援隊を引き連れて、慶喜を襲撃して自分も死ぬ」
さらには、もし後藤の献策が失敗して、
「大政奉還の機会を逸したならば・・・
その罪は天が許さないだろうから、もはや生きていられないだろう」
と、後藤を脅迫するかのような、ことさえ書いている。
なみなみの今を零してはならぬ 山本早苗

大政奉還が発せられた、二条城二の丸御殿大広間
大事にあたる際のこうした迫力、覚悟もまた龍馬の一面を語っている。
龍馬は決して、単純な平和論者ではなかったし、
時代の大変革が起こる過程では、
「ある程度の犠牲が出るのは止むを得ない」 と考えるリアリストでもあったのだ。
そして、後藤の献策をうけた慶喜は、その日のうちに、
在京40藩の重臣を二条城に招集し、「政権返上」を告げる。
翌14日、「大政奉還上表」が朝廷に提出され、
15日の朝議において、勅許が下り、大政奉還は正式に成立する。
ジンジンと来るバリトンのエピローグ 山口ろっぱ

もはや賽は投げられた。
時代状況は、倒幕へと向かう激流となり、
龍馬もまた、その激流の中に身を置くことになる。
言葉などいらない目の前の海で 立蔵信子
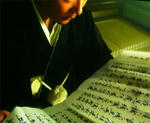
『龍馬伝』・第47回-「大政奉還」 あらすじ
大政奉還へ、
容堂(近藤正臣)の書いた建白書を受け取った将軍・慶喜(田中哲司)は動揺する。
龍馬(福山雅治)は、慶喜に一番近い永井玄蕃頭(石橋蓮司)に直接会い、
「徳川家を存続するためにはこれしかない」
と説き、慶喜を説得してくれと頼む。
あきらめたらあかん苦労が無に帰る 鈴木栄子

弥太郎(香川照之)は、「戦が始まり武器が高く売れるようになる」
と、銃を買い占めていたが、
ふと、「龍馬なら大政奉還を成し遂げる」
と思い立ち、方針転換して手持ちの銃を売りに転じる。
一方、永井玄蕃頭に後押しされ、慶喜は二条城に諸藩を集め、
大政奉還を問うが、どの藩も反対しない。
時流を悟った慶喜は、大政奉還を決意する。
視力0.1で見る時刻表 井上一筒

知らせを待つ龍馬のもとに、勝(武田鉄矢)が訪れる。
幕臣である勝は、龍馬がなくそうとする幕府の人々の将来を憂うが、
龍馬は、
「皆が同じように、自分の食いぶちを自分で稼ぐ世の中になる」
と返す。
そこへ大政奉還の知らせが舞い込み、
新しい日本の夜明けに歓喜する龍馬。
吠えて吠えて吠えて維新の風が吹く 島尾政男

しかし、武力討幕を目指してきた”薩摩や長州”、
幕府に忠誠を誓う”新選組”、
そして、揺るぎないはずだった”権力を奪われた将軍、幕臣たち”が、
自分たちの道をことごとく邪魔をする、
龍馬の命を狙い始める。
≪「余談」ー龍馬は大政奉還後の政権を慶喜が主導することを想定していた。
しかし、慶喜本人が、龍馬という人物の存在を知ったのは、
明治に入ってからであった≫
生と死の中ほどに立つ彼岸花 前田扶美代
≪豆辞典 一の間、二の間を合わせると92畳の大きさ≫
 [5回]
[5回]
