しゃっくりを短く曲げる銀細工 井上一筒

「慶長10年からの4年間の出来事を描く」
慶長10年(1605)
4月、秀頼が右大臣となり、秀忠が2代将軍になった。
秀忠の将軍就任ついては、徳川家の、
「豊臣に天下を返すつもりはない」
という意思表示として、とらえられている。
しかし、これは間違った解釈である。
というのも、この時点での統治は、
「二重合議制」であって、
「徳川が豊臣の大老として、天下の統治を預かっている」
という建前は、否定されていないからだ。
眼や鼻の置き場をちょっと間違える 中野六助
この年の 5月、「秀忠の将軍宣下を祝いに上洛しないか」
という家康からの打診に、茶々が怒った。
「無理にと言うなら、秀頼と心中する」
などと、茶々は、息巻いた。
ただ、茶々が、怒り反対したのは、
「秀頼が秀忠に、臣従することになるからだ」
と解釈するのには、多少の無理があるのではないか。
≪のちに、二条城で家康と秀頼が会見した時も、
いろいろな儀礼上の配慮はあったが、
臣従といったもので、なかった例があるように・・・≫
パロデイーにするには中途半端です 美馬りゅうこ

秀 頼
仮にこの時に、秀頼が上洛しても、
公家衆と将軍が会う時と同じで、官位の高い秀頼が、
秀忠の下に位置することには、ならなかったはずである。
茶々の心配は、
「秀頼の身に何か起きないか、
そのまま京都とか、伏見に留めおかれるのではないか」
ということだった。
こうした理由で、茶々は、秀頼の上洛を毅然と拒否している。
屋根裏を君はときどき散歩する 寺島洋子

淀 殿
その後の茶々の親馬鹿ぶりを、
推察しても分かる通り、、
茶々は、秀頼が自分と引き離されることを、
極端におそれたのだ。
このことに家康も、
「少々、刺激が強すぎた」
と思ったのか、六男・忠輝を大坂に派遣して秀頼に
拝謁させるなど慰撫につとめている。
6月 に、高台院が三本木から、高台院に移る。
悪癖は星に行ったり帰ったり くんじろう
慶長11年(1606)
3月、高次の妹・マグダレナが、若くして亡くなった。
姑のマリアは、大変これを悲しみ、
朽木宣綱を強引に説き伏せて、
京都四条に新しく完成したイエズス会の聖堂で、
器楽の合奏隊まで用意した、盛大な葬儀をおこなった。
ソプラノもアルトもあって虫時雨 合田瑠美子
ところが、このことを知って怒ったのが、
またまた茶々である。
キリシタンに改宗した初とは違い、
茶々は、とても信心深い仏教徒である。
僧侶たちから頼まれたこともあり、
「家康にキリシタン禁制を強化するように」
と要求、片桐且元が高札を立てて、禁制を掲げた。
≪もっとも、翌年には、秀頼の意向もあり、少し緩和されている≫
記憶から遠いところに置くナイフ 瀬川瑞紀

お江ー崇源院
6月、江戸ではお江が次男を出産する。
二男・国松である。
のちの駿河大納言忠長だ。
長男・竹千代を、お福にとられてしまったお江が、
この子を可愛がったのは、自然の成り行きだろう。
宇喜多秀家が、関が原の戦いの後、
薩摩に隠れていたが、
島津と徳川の関係が、安定したのを機会に出頭し、
八丈島に流されることになったのも、この年である。
手の上に手を置くやわらかい時間 片岡加代
慶長12年(1607)
家康、富士山が美しく見える駿府城に引っ越す。
家康が江戸城に滞在した時期は、それほど長くなく、
将軍になってからも、
秀忠に将軍を譲り大御所になってからも、
伏見城に住んでいた。
実務も秀忠が行うようになり、
江戸と連絡を取りやすくするための、手段でもあった。
≪家康が江戸に近く住むのは、江には煙たがったが・・・≫
倫理観少し削って生きてみる 高橋謡子
この頃、茶々が京都近辺に盛んに、社寺を造営する。
特に、高台院の頼みでもある北野天満宮は、
今も残る華麗で、見事な権現造りなものになっている。
これらは家康が、
「豊臣の財力を減らす目的」 があったものだが、
かえって、豊臣の人気をあげることとなり、
家康にとっては、忌々しいことになってしまった。
そして 10月 には、
お江が五女・和子(東福門院)を出産する。
万緑の中で虫歯がうずきだす 三村一子
慶長13年(1608)
大坂・夏の陣のあとの、慶長20年5月、
8歳の少年が処刑された。
秀頼の隠し子で、この年に生まれた” 国松 "である。
秀頼が16歳のときの子供で、
秀頼が成人したところへ、お側につけた女性が、
妊娠してしまったのだ。
この年の 2月、秀頼が疱瘡にかかった。
「北野天満宮造営の功徳で助かった」ということで、
秀頼も,多くの社寺の造営をはじめた。
反省のドアを閉めたり開いたり 小西カツヱ

高 台 院
慶長14年(1609)
8月、高台院の兄であり、
小早川秀秋の父でもある木下家定が死ぬ。
その遺領をめぐって、騒動が起こった。
当初、勝俊・利房兄弟で折半して、
相続することになっていたのだが、
高台院が、お気に入りの勝俊に,
「すべて継がせるよう」 に命じた。
それを聞いた家康が、自分に相談もなく、
そんなことを命じた高台院を、
「耄碌している」
と罵倒し、木下家を取り潰してしまった。
≪いわゆる家康と高台院の親密度は、この程度のものということか≫
その向こうはジンベイザメの領分 山口ろっぱ

初ー常光院
5月3日、初の夫・高次が47歳の若さで亡くなる。
京極家は、長男・忠高が跡を継いだ。
夫を亡くし、剃髪して「常高院」となった初は、
夫・高次の菩提を弔いつつ、関が原での心痛を胸に、
徳川・豊臣両家の「和睦の使者」となるべく、
懸命に奔走した。
「淀と江の絆をつなぐのは、自分しかいない・・・」
その一心で、女の身でありながら、
両家の間を行き来する。
ただひたすら姉妹の絆を保つため、
身を呈して戦国の世を駆けたのだ。
この年、秀頼の姫が生まれている。
のちの天秀尼である。
うつくしく跳べたら昆布茶を飲もう 田中博造


大河ドラマ・「お江」-第39回-「運命の対面」 あらすじ
秀忠(向井理)が、
征夷大将軍に就任すると、
江(上野樹里)は、
" 御台所 ”という敬称で呼ばれるようになった。
大姥局(加賀まりこ)は、江に、釘を刺す。
「武家のおなごでは日の本一である御台所として、
ふさわしく振る舞うよう」 と。
江としては、我が子・竹千代(橋爪龍)を、
好きな時に抱くこともできないのに、
「何が日の本一じゃ」 という思いだった。
価値観の違い空気になれませぬ 山本昌乃

ともあれ、江は、武家の女性の頂点に立ったのだ。
やがて、江は2人目の男子・国松を産む。
またもや、男子を授かった徳川家は、
竹千代をめぐる江と福(富田靖子)の確執こそ、
続いていたものの、
まず順風満帆といってよかった。
それからは川の流れにゆだねてる 杉野恭子

一方、淀(宮沢りえ)は、国松の誕生を知り、
豊臣家の当主・秀頼(太賀)に、
まだ世継ぎがいないことが、気になりはじめる。
徳川家が支配体制を固めていく中で、
豊臣家の威光を保つには、
できるだけ早く、世継ぎをもうけるべきではないか。
悩んだ末、淀は秀頼に側室をとらせる。
掌の黒子は北斗七星より自由 蟹口和枝
正室の千(芦田愛菜)は、
子を産むにはまだ幼すぎたのだ。
だがこの措置は、江に、
「娘と思って育てる」
と約束して迎え入れた千の心を、
傷つけてしまいかねないもの。
淀は、徳川家への対抗心から、
非情な決断を下したのである。
遺伝子の部品ひとつが足りません 清水すみれ

家康(北大路欣也)は、そんな淀をさらに追い詰める。
京に上る自分に、
「挨拶すべし」 と秀頼に上洛を求めたのだ。
それは明らかに、豊臣家を下に見ての要求だった・・・。
加えて家康は、新将軍・秀忠の名のもと、
新たな江戸城の普請と、江戸の町づくりを諸大名に命じ、
徳川幕府の力を天下に見せつける。
安定剤が寒い畳を転がって 森中惠美子
秀忠は、なんとか豊臣家との融和を図ろうと、
完成した城には、家康に入ってもらい、自分は、
「江とともに大坂に近い伏見城に移りたい」
と主張するが、家康は息子の甘い考えを一蹴。
そのうえで、自分はなじみのある駿府に城を築き、
そこで、隠居すると言い出す。 だが、
隠居が表向きのことであるのを、秀忠は見抜いていた。
家康は、江戸と大坂の間にある駿府で、
双方ににらみをきかせながら、
政治の実権を、握り続けるつもりだったのだ。
自分らしさの裏も表も見せている 森 廣子
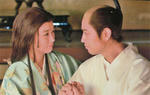
一方、関が原戦いでの功績により、家康から、
若狭国の城主・高次(斎藤工)と初(水川あさみ)は、
若狭小浜で、以来、平穏に暮していた。
だが、そんな2人の幸せな暮らしに、終りが訪れる。
高次が病に倒れ、初の献身的な看病もむなしく、
世を去るのだ。
生涯の一誌ありけり天の川 大西泰世
死の直前、関が原の戦いで、
結果的に豊臣家を裏切る形となったことを、
「今も申し訳なく思っている」
と明かした高次。
その思いが、
夫亡き後、落飾して「常高院」と号する初の人生に、
大きな影響を与えることになる。
こころが疲れたら物置きに閉じ籠る 新家完司
 [4回]
[4回]
