[ 176]
[ 177]
[ 178]
[ 179]
[ 180]
[ 181]
[ 182]
[ 183]
[ 184]
[ 185]
[ 186]
芒野とねずみの肝とアンチモン 井上一筒
 悪源太義平
源氏の棟梁・源義朝の長男。
悪源太義平
源氏の棟梁・源義朝の長男。
15歳のとき義平は、大蔵合戦で武名をあげ、
「鎌倉悪源太」と呼ばれるようになる。
(クリックすると画面は大きくなります)
「大蔵合戦」
久寿2年(1155年)、義平は父・義朝が叔父・義賢と対立した際に、
義賢の居館・武蔵国の「大蔵館」を急襲し、
義賢や義賢の舅・秩父重隆を討ちとった事件。
このとき、2歳だった源義賢の子・駒王丸は、斎藤実盛の計らいで、
信濃国の中原兼遠のもとに逃がれた。
この駒王丸が、後の木曾義仲である。
義仲は命の恩人である実盛と、 「大蔵合戦」から28年後の、
「篠原の戦い」において首実検の場で、
悲劇的な対面(再会)をしている。
首筋に歯型くっきり虫しぐれ 増田えんじぇる

「主流派対反主流派」
保元元年(1156)7月2日、鳥羽院が崩御した。
鳥羽院の遺志を継いだ美福門院は、
後白河天皇・守仁親王・関白・藤原忠通を中心に、
鳥羽院旧臣や後白河天皇近臣を束ねて、
派閥の解体を防ぐ一方で、
鳥羽院・美福門院の意向を受けた武家・
平清盛・源義朝・足利義康・源頼政・源重成・
平実俊・関信兼、などに参集を命じた。
ひとりづつ味方につけていく粘り 立蔵信子
一方、反主流派は、
崇徳天皇・左大臣・藤原頼長を中心に、
彼らの側近や摂関家に仕える、
源為義・平忠正、大和源氏の宇野親治といった、
京の武者や、為義が呼び寄せた家人に限られていた。
河内源氏には、為義が頼賢を嫡子に選んだことで、
長子・義朝とのあいだに軋轢があり、
鳥羽院は、そこにつけ込んで、
義朝を、院政派(主流派)に引き入れた。
擬態して別の世界で生きてみる 三村一子
両者の衝突は、久寿2年に大蔵館にいた源義賢を、
悪源太義平が急襲して討ち取った、
「大蔵合戦」となってあらわれた。
南関東を勢力圏に収めつつあった義朝の離反は、
大きな痛手であった。
最初から知っていたんだこの痛さ 安土理恵

平忠盛の後家・池禅尼は、
崇徳院の乳母であったが、
美福門院の勝利を確信し、息子・頼盛に対して、
「清盛とともに天皇方に参ずるよう」 命じた。
家族同様の乳母子にまで離反された崇徳上皇は、
予想外の事態に驚き、
白河北殿に移って、武士を参集させようとしたが、
美福門院はいち早く、
検非違使を京の入口に派遣して、道を封鎖した。
思ったとおり怒ってる泣いている 奥山晴生
7月6日、宇野親冶の子は、
白河北殿に向かおうとしたが、
法住寺付近で平基盛と合戦となり、討ち取られた。
美福門院の手際のよさは、
鳥羽院が最期を意識し始めたころから、
崇徳上皇一派を、武力で制圧する、
意図を持っていたと思われる。
正面の顔がやっぱり阿修羅像 小林満寿夫
7月10日、両派の軍勢は鴨川を挟んで対峙した。
一触即発の情勢に、京の町に緊張が走る。
上皇側は白河北殿、天皇側は高松殿を拠点とした。
そして、7月11日未明に合戦は始まった。
青空へバケツ一杯汲みに行く 和田洋子
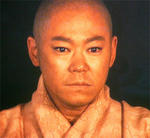
美福門院は、藤原信西と源義朝が、
先制攻撃を主張したので、
御所の警固は、官人に委せ、
武家は、新院御所攻撃に向かわせた。
合戦にいたる政治的な駆け引きは、
鳥羽院の遺志を継いだ美福門院が主導してきたが、
いざ合戦になると、
後白河天皇の乳母夫・藤原信西の手に移っていった。
丁寧に畳まれている蚊帳の外 笠嶋恵美子
崇徳院側では、源為義が、
「白河北殿を守り切れないことはないが、
万一の時には南都に移り、
源家の家人を集めて、京に攻め込むのがよい」
と主張した。
この会議が続いてるところで、
物見に出していた武者所の官人から、
敵が動いたと報告が入った。
空き缶がころげ出てくる左耳 岩田多佳子

平家の微妙な立場を反映して、
鳥羽院の容態が悪化したとき、
御所を守るために召集された武士の中に、
清盛の姿はなかった。
鳥羽の恩顧に報いるか、
崇徳との縁故を優先するのか、
自身の決断が、一門の運命を左右するということを、
清盛自身は痛切に感じていた。
断捨離とニアミスをした薬指 和田洋子
もともと後白河天皇は、皇子の二条が即位するまでの、
「中継ぎ」として擁立された。
ただし、中継ぎとはいえ、天皇である以上、
朝廷の頂点に君臨する絶対的な権威、
であることにかわりはない。
後白河の兄である崇徳に院政を行なう資格はなく、
崇徳方につくことは『賊軍』への転落を意味する。
風の要素たるべく不定愁訴 山口ろっぱ
清盛は悩み抜いた。
そして、清盛が結論を出したのは、
鳥羽の死から三日後の、7月5日だった。
京随一の勢力を誇る清盛が、
どちら側につくか、その戦力の差をもって、
戦いの帰趨は、始まる前から、決していた。
足首を19センチ開放す 小嶋くまひこ [5回] [5回]
|
最新記事
(11/09)
(11/02)
(10/26)
(10/19)
(10/12)
|
