美しい車力熊野の湯葉へ来る 説教節
「詠史川柳」-江戸の景色 湯屋ー② 山東京伝 黄表紙

(すべての画像は拡大してご覧ください)
『賢愚湊銭湯新話』
曲亭馬琴の師であり、また半世紀早く金の取れる唯一の作家として
活躍した山東京伝は、遊里短編小説としての洒落本の第一人者であり、
浪漫的な伝奇小説、読本、そして黄表紙においても一流の作者である。
その京伝が著した『賢愚湊銭湯新話』は、享和二年(1802)出版の
黄表紙で、寛政改革時に厳しい出版取締令が出た後の出版であるため、
教訓的姿勢が濃厚であり、文芸的価値の点では、高く評価されないが、
江戸文化における「銭湯」を知るための資料として貴重なものである。
ついでながら黄表紙について、絵と文とを同時に並行して見、読むと
いうところは、現代の劇画に似ているが、軽妙、洒脱、機智に溢れて、
泰平の江戸の住人の興味を、そのまま反映しているところに、特殊な
価値を有するものである。
黄表紙とは、こんなものであったことを絵と合せ読んでみてください。

賓頭盧尊者(びんずるそんじゃ)と湯屋の湯番は高きところに上りゐて、
その形よく似たり、賓頭盧は衆生を済度するが役目、湯番は人の出入り
を守るが役目なり。これ軽き役にあらず、たとはゞ天道様ありて、人の
善悪を見分け給うがごとし。然れども湯番はもとが凡夫なれば、をり々
居眠りをして、出入の人に草履を履き違へさせ、帯を間違へさせること
などもあれど、天道様は居眠りなどはし玉わず、つねに日月の眼を押し
開きて、人の善悪を見分け玉ふ故に、あなたに少しも誤りあることなし。
天道様が見通しといふは、此故なり。
「わしが草履をかぼちゃのやうな頭のぢいさまが履きちがへて行ったと
いふことだ。裸足では帰られず、これは当惑千万だ。
ぞうりでかぼちゃが当惑とは、此の事であんべい」

定
一、神儒仏の教は不申及主人父母の命をかたく相守可申候事。
一、身の用心大切に可仕候事。
一、極老の御方貪欲の源 入被成間敷(いりなされまじく)候。
一、浮気と云う悪敷病ある御方、色里へ御入込御無用の事。
一、心に奢りの風立候節は、何時成共御断なく身上しまわせ申候。
一、金銀其外大切の品御持参の御方、旅の夜道御無用の事。
一、名聞利欲の喧嘩口論、喜怒哀楽の高声御無用の事。
一、魂魄(こんばく)の失せ物不存候。
一、地水火風のあづかり物不仕候。
月 日
定
一、ひとむかし 拾ねん
一、子供のうち 八ねん
一、わかざかり 廿ねん
一、札銭人間一生ニ付 五十枚
一、陰徳をほどこす時は人間一生二度入りの御方となり、
百年の寿命も保たれ申候。
一、右の通りご承知の上、正直に世渡り可被成候。
月 日

そもそも銭湯の風呂口を石榴口といふは、むかし鬼子母神千人の子を
腹のこの中へ隠し玉ひしことあり。
風呂口も千人万人の人を隠しいるゝところなれば、鬼子母神の縁により
て石榴口と名付けたるよし。又諸人風呂へ這入る姿は蟒蛇(うわばみ)
に呑まるゝやうなりとて、蛇喰口とも名づくるよし、つくづく考ふるに、
正直なる人は楽しみ多く、邪なる人、愚痴なる人は苦労多し。
故に邪苦労愚痴なるべし。
されど尊きも賎しき湯へ這い入る時は裸となる。
これ天地自然の姿にて、風呂口より出る人は、産湯を浴びて生れ出るが
如く、着物を脱捨てて風呂へ這入る人は、この世金銀家財を残し置きて、
死して沐浴を受くるがごとし。
いかほど不精な人も此の二度の湯はぜひ々浴びねばならず、
死あるが故に生あり、生あるが故に死あり。
生死一重が儘ならぬと唄いしも此の事なり。

「すべるは すべるは どこい どこい。
いちばん滑ってくんさるなら、かたじけ流しの真ン中だあも さ。
こいつは朝湯なのせりふだ。
「おぎゃあ おぎゃあ おぎゃあ。だが、ふく坊は風呂へ這入って
いい子になったぞよ。かかァが乳をためて待っていよふぞ。
「ことしは静かな良い春じゃ。去年中の心の垢を洗い落として、
恵方参りとでかけやう。

諸人入込の銭湯は、貴賤老若混雑の世界によく似たり。
初会の床の当推量、辻占いの八つ当たりも、大概は衣装着物で見てとる
なれど、湯へ這入る人はみな裸なれば、貴賤上下おしなめて見分け難く、
襟に瘕(なまづ)のできたは鰻屋の隣の人か、顔に雀斑(そばかす)の
あるは饂飩屋(うどんや)のかみ様か、額に疥(はたけ)、肩に田虫が
できたは百姓の息子か、鳩胸は豆屋の亭主か、鮫肌は蒲鉾屋の隠居か、
手の長い人には油断なるまい、内股に膏薬を貼った人には滅多なことは
言われまい。小賓(こびん)に痣のある人は景清が末葉ならん。
背中に竜を彫った人は水滸伝の九紋龍が子孫かと、これ皆当推量の目利
きにして、まことの目利きにあらず。
人の心の善悪もなりふり顔つきで見分けがたきこと、この道理なり。
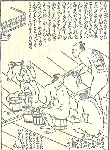
「お前の背中は猫背中だから、鼠の糞のような垢がよれます。
「二百はずむからずいぶん糠袋を買いつかんで、脂垢を西の海へさらり
と流してくりやれ。よく、洗いましょ、垢落しだ。
「南無金毘羅大権現大平饂飩蕎麦か。
「あなたは桂馬様ではございませんか。お飛車しや 々
「かやうに金を握って申すは失礼でござるが、貴公の歩はお達者かの。

朝湯の人の身にひゝりとしみるは、此ごとく朝から家業を身にしみろと
いふ教え、仏嫌いな爺様も、湯へ這入れば我知らず南無阿弥陀南無阿弥
陀と念仏を申す。皆これ銭湯の湯徳也。
「人裸になれば貴賤上下を分け難し、然れども、土佐裃に外記袴、
半太羽織に義太股引と、一ㇳ口づつの湯屋浄瑠璃、豊後正伝唄祭文、
潮来四つ竹新内節、猫じゃ猫じゃに到るまで、ただその好む所によりて、
人柄の上下が知れるなり。
隅にいる人がいふ。
「さつきから聞いていれば、謡いもあればめりやすもあり。
触り文句に責念仏,神祇釈教恋無常、これはとんだ乗合舟だ。
「一家も一門もない、きなかものでござい。ごめんなさいまし。

「これは強勢に熱い湯だ。
焦熱地獄の銅壷の蓋か、不動様の背中ときてゐる。
「たがひの心うちとけて、うわべはとけぬ五大力、さはさりながら、
変る色なき御風情っさ。
「あゝいゝ加減な湯じゃ。これがほんの極楽往生、あゝ南無阿弥陀 々。
「おぬいは涙せきあへず。恋は女子の癪の種。
「阿蘇の宮の神主友成とは我が事なり。

湯屋の流しも折々砂をつけて磨かざれば、人を滑らして大きな怪我を
させることある故、毎日々怠らずこれを磨くなり。
人の渡世も亦折々気をつけ、十露盤の玉をもって磨かざれば、
商いに上滑りがして人の身代に怪我をさせるのみにあらず、
我が家蔵の腰をぶんぬき、大工の骨接ぎ、左官の鏝療治(こてりょうじ)
でも治らず、晦日物前に打身がおこりて、終に病のもととなる。
怠らず商売を磨くべし。
「玉磨かざれば光なしだ。流しも洗わねば、溝板同然だ。
「さっさとこすれや、節季候 節季候。

草木こころなしといへども湯にも心あり。人の心には私ありて、
湯の心には私なし。それはまた何故といふに、人ひそかに湯の中にて
放屁する時は、直にぶくぶくと音がして、泡のやうなるもの浮み出る。
これすなわはち人の心に私ありて、湯の心に私なき証拠なり。
「もふ昼だそふで、腹が少し北山の武者所だ。酒を一杯熊谷なら、
せめて二八の敦盛でもしてやりたい。
「かう毎日柄杓を持つが商売とは、梅が枝が川留めにあったやうだ。
芝居だと手裏剣を受け止めて、巡礼に御報謝という役だ。

芝居にも土用休みあり。職人にも煙草休みあり。
湯屋にも定まれる休み日があって、風呂場を乾かし、小桶を干し、
風を入れ、日に照らすは、水に腐らせぬ用心なり。
大酒を好むものも此の道理にて、毎日々酒浸しになって休み日が無ひと、
腹が小桶のやうに張って、鼻が石榴口のやうに赤くなり、
壁のあばら骨があらわれ、四十四の骨の柱が腐って、命のを失ふこと
目前なり。慎みて大酒を好むべからず。
「此の本には女が少ないとて、おいら二人が此処へ書かれたのさ。
畢竟(ひっきょう)作者のおさきだま。
両方から駒下駄を履いた女中が来て、
「おやおやどうしやうの、休みじゃ無へと思ったに。
「わっちもさ。照らされたよ。どうしやうの。
と二人ながら下駄で来た故、げたげたと笑ふ。これを湯屋笑ひといふ。

湯屋の若い衆、休み日に奢りかける。
「かう奢っては明日の貰い湯を台無しにするぞよ。
「はて酔ったら儘の川千鳥、足がひょろつくぶんの事だ。
もふ一つ もふ一つ。
絵の△は、京伝の宣伝が書いてある。
一、忠臣水滸伝 売り出し中、お求めのほどよろしく。
一、京伝煙草入新型 京伝は煙草入れを発明したことで有名。

湯屋にも仁義五常あり。
湯をもって人を温め、草臥れ(くたびれ)を休めるは仁なり。
人の桶に手をかけぬは義なり。
田舎者でござい、冷え者でござい、御免なさいとは礼なり。
糠洗い粉軽石糸瓜の皮で垢を落すは智なり。
風呂の板を叩けば承知して水をうめる、これ信なり。
「湯は陽にして天の象(かたち)による故に、円き柄杓をもって円き
小桶に汲み入るゝ。水は陰にして地の象による故に、四角な水槽より
四角な升をもって汲みとる。
湯は男なり。水は女なり。男の熱き熱湯の中へ、女の冷き水をうめれば、
よき加減の湯となる。夫婦和合の道理、此ごとし。
熱湯の儘にて使へば火傷をする。水ばかりでは風邪を引くなり。

「動左衛門様、もうお上がりか。お前は烏の行水じゃの。
「商人は手拭を絞るにも、身の脂をしぼる気にならねばならぬ。
「けふもだいぶん湯が込むかへ。
「湯へ這入る所は誰でも、ざまの悪いもので、湯のよる処へは、ざまが
よるとは此の事だ。
「そりゃ焼十能でござい。御免なさいまし。

男湯と女湯の分かるは、男女別あるの道理なり。
楊貴妃が驪山(りざん)の浴室には、玄宗の涎を流し、
塩谷が妻の湯上りには、師直のうつつをぬかす。
これらは皆煩悩の垢なれど、光明皇后は千人の垢を流して、仏の化身に
あひし事もあり。
煩悩あれば菩提あり、盆前もあれば大晦日もある道理なり。
「そもそも湯上りの時美しき女はまことの美人なり。雀斑(そばかす)
疥(はたけ)、疣(いぼ)、黒子、頬の赤きも大痘痕(あばた)も、
紅粉白粉でくろめれば、相応に見ゆるものなり。人の心もまずその如く
追従軽薄の紅粉白粉で彩しは真の心にあらず。
正直の糠袋で洗ひあげたる所が無疵の実心なり。
此の二人娘、粂三かお七といふ気取りで自惚れている。
「なんだか悪臭い匂いがするのう。
「あれは水虫へつける薬に糠の脂をとるのさ。
「お竹さんを人がいゝいゝといふが、気が知れねへよ。
「そふさ。あの横顔を見なゝ。精霊さまの馬を見たやうだ。
「これから帰って狆に湯を浴びせてあらふ。

「さあ々湯へ這入りましょ。坊やいゝ子だぞ 々。
「だいぶ御成人でござります。おとなしいお子じゃ。
「おつぼさん待ちなよ。付合いを知らねへ子だのふ。

湯の中で温まれば酒麩のやうに縮まった睾丸も自然とだらけてくる。
人の身代も内証が温まってくると、そろそろ金袋がだらけて、思わぬ
無駄銭を使ふかも、盛って入る時は、又盛って出づる道理。
ただ銭金を湯水のやうに使えば、じきさま休み日の湯屋のやうに、
身代の内証が空っぽしやぎとなるは目前なり。
「あゝいい心持ちだ。さっぱりとしてよいぞ々。
おれが形は干し大根で作った文覚上人ときている。
「御隠居様この頃は碁はどうでござります。
「これ小僧、冗談をするな。小桶戻れば千里も一里だ。

「これはいかいこと小桶が並んだ。
小人島で沢庵漬の問屋をするようだ。
「これはけしからぬ混みやう。おらが方へおはちの廻るは夜が遥かだ。

長湯を好む老人などは、たまたま湯気に上りて目をまわすことなどあれ
ども、気付けを用ゆるに及ばず。
顔へ水を吹きかけるとたちまち気がつくなり。
銭湯人殺さずとは此の故ならん。
「誰だと思ったら八百屋のお爺さんか、やれやれあんまり長湯をなさる
からの事じゃ。長湯もあれば短湯もあるは八百屋の隠居様、
これもうし気が付きましたか、気がつきましたか。
「頭が唐茄子のやうで、鼻が胡桃のやうで、手足が干し大根のやうで、
睾丸が何首烏(かしう)のやうだから、八百屋のお爺さんだと思った。

ずっと大昔は、湯屋で物を掠めたがる者もありけるよし。
もしさやうの者ある時は、顔や体へ一面に鍋墨をなすって、辱しめたる
となり、これ何故なれば、崑崙国(チャンバ王国)の人は俗気多く、
珊瑚樹などを奪いて逃げ出す所、絵にもよく書くやつなり。
故に黒ん坊となして、恥を与へけるとぞ。
「まづ此の薪雑把を食わせるがいゝ。
「こいつはとんと黒ん坊の生捕りときている。
珊瑚樹のかわり十能を見知らせてくりやう。どっちも赤いものだ。
「憎い八つ目鰻だ。おもいれ油をとってやれ。

湯屋の二階で売る駄菓子を食ふにも謂われなきにあらず。
教化別伝不立文盲な咄をして尻を腐らせる人は、達磨糖をしてやり、
お釈迦様の開帳話をしながら、さがおこしを食ふもあり。
生姜糖をしてやる薬取りもあり。
昼寝の夢のお目覚ましに粟の岩おこしを食ふもあり。
頭巾を被った人が大黒煎餅をせしめ、大ころばしを食って雪隠へ行きた
くなるお爺が、飴一本四文、大福餅あったかいにも故事来歴あるべし。

「今日はよい天気でござります。香煎をあがりまし。
「明日は大師河原へ行くつもりだが、気はなしか。
「昨日は堀の内へ参って、強勢に草臥れた。遠いぞ 々。
「番公変ることもないか。
「八兵衛が来るはずだが、まだ見へねへ。

「わりゃァよくおれが睾丸を糠袋と間違へてつかんだな。
それで湯をぶっかけたが何とした。此の黒砂糖の固まりめ。
柿のやうな眼を剥きだしても怖かあねへぞ。
「こいつが々、わりゃァまたおれが眼の柿のやうなをどの眼で見た。
悪く笛を鳴らすが最後、犬に褌を咥へさせ大津の宿へしたにやるぞよ。
漆掻きの尻を杖で突つくとはちがふぞよ。
「これさ二人ともきん玉があぶないあぶない。
蓼の虫葵に移らずといへども、襤褸襦袢より羽二重の小袖へも移るは
湯屋の虱なり。
人も又此の湯屋の虱の如く、襤褸襦袢の賎しきより羽二重の尊きへも
移らざるといふことなし。

もし旦那、それそれ葵虱が二つ胴に二匹連れ、裾までよって這います。
それからご覧じろ。こいつは続きの二匹だはへ。
「はて合点のゆかぬ。
裁(き)りたての小袖へ千手観音のあらわれ給ふは心得ぬ。
察する所、時は弥生の半なれば、こいつ花見虱じゃな。
何にもせよ、むさいこの場の風呂屋じゃなァ。

大晦日の夜はいづくの湯屋も夜通しなるが、東雲のころ、風呂の栓を
抜きけるに、悪臭き匂いして、湯いちどきに流れ出で、湯気霧の如く
立ち昇るうちに、異形の物あらわれ出でたり、角は鼠の糞の如く、
面は軽石の如く、歯はつるしてある櫛の如く、手は鋏の如く、
胴は小桶の如く、足は手拭・糠袋に似て、糸瓜の皮の褌を締めたる鬼、
洗粉の如き生臭き毒気を吐きて、すっくりと立ちたり。
これをいかなる物と思ふに、一年三百六十日の間、毎日毎日入りくる
人の洗い流したる垢の亡魂なり。

垢の亡魂がいふ。
「色の黒き男色男にならんと洗粉にて磨きたるは、これ色欲の垢なり。
金の番をする爺様が長き爪にて掻き流したるは、これ貪欲の垢なり。
その他不幸不忠の垢、不義不仁の垢は申すに及ばず、高慢自惚の垢
悋気嫉妬の垢、憎い可愛いの垢、嬉し悲しの垢、追従軽薄の垢あり
て、一人として欲垢に汚れざるものなし。
その垢積り積りては此の様な鬼となって一生を苦しむぞや。
「これ申し番頭どの、我が身欲垢の鬼となり、焦熱地獄の釜風呂の底
に沈みて苦しむことを、世の人に告げて心のうちの欲垢を溜めぬや
うに、よくよく伝えて下され。
そのお礼には万歳で一つ祝っておきませう。

「欲垢に御万歳とは、お湯屋も栄へてましんます。
といいつつ小桶の尻をぽん々と叩き、
消し炭の火鉢のうちを掻き消す如く失せにけり。
「湯屋はけしからぬ化物だ。
「二日の初湯松の内、桃の節句や菖蒲風呂、盆の燈籠二度の貰い湯、
一年中の人の垢、積り積りて此の姿、
あゝ苦ししに牡丹で石榴口の絵解きだなァ。
「なんだか無性にめでたい めでたい。

夫天地間は湯室(ゆや)で看(みた)よりも大にして。
量り得がたきこと。浴盤を彭翁菜(ごぼう)で探るが如く。
一切衆生湊集(いりごみ)欲界。恰も銭湯の光景に似たり。
邪心悪念人心の垢。箇々十泉を以って。いかでも洗い落すべき。
琉球の洗粉、朝鮮の水石(軽石)。
紅毛(オランダ)の天糸瓜皮は用いるにたらず。
唯神儒の糠袋。仏老の垢擦り。よく心裡の垢をおとす。
に浴しぶうしぶういふ険悍(ちうつばら)も。 蛮の垢を去り。
身にもろもろの惰的(ぶしょうもの)も。心に日頃の垢をたけな。
あらひ玉へきよめ玉へとまうす。
享和壬戌春 東都 山東京伝誌
【詠史川柳】 誰のことを言っているのか分かればかなりの歴史通
湯治場の評判になる車引き
車止めすこぶる困る照手姫
照手姫毎日そこら握って見
この主人公は、誰の事か今回は書いておりません。
 [3回]
[3回]
